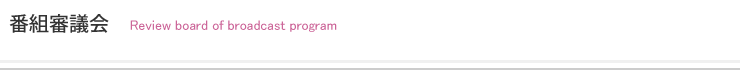KKB鹿児島放送の番組審議会は、鹿児島市立美術館館長の楠元香代子さんを委員長に県内の有識者7人で構成され、放送番組の向上と適正化を目指して意見を交わしています。
今回は、「地上波テレビとコンプライアンス〜テレビの信頼回復にむけて〜」をテーマに審議しました。主な内容は次のとおりです。
審議課題
「地上波テレビとコンプライアンス〜テレビの信頼回復にむけて〜」
- テレビがコンプライアンスに関して信頼を失っているとは考えていない。自分が行っている業務や行為が本当に世の中のためになっているのか、正しいのかなどの視点で考えていけば、メディアの役割をきちんと果たせていけると思う。
- 公的な立場で信頼できる情報が欲しい、安心して発信できるメディアであって欲しいという世間の期待がある。事が起こると、萎縮したりして、回復に時間がかかると思うが、着実に一つずつ積み上げていく事や、人の話をよく聞いて、変えなければいけないことがあるのではないか。
- 市民の立場に立つという覚悟が必要。誰でも情報発信できる現代において人々が求めているのは信頼できる、市民が知りたい情報に答えてくれるメディア。昨年、鹿児島県警に関連する番組を放送したが、信頼回復に向けての第一歩であったと思う。メディアに携わっていることの誇りと自信を持って、自虐的になるのではなく、一つ一つの積み重ねで信頼を回復して欲しい。
- ISOが定める七つの原則にのっとった企業活動を、他の企業に比べてより厳格に遵守した経営を実践するということがメディアとしての社会的責任を果たすことにつながる。各テレビ局が不断の見直しを進め、改善した事項があれば対外的に公表していくなどの積み重ねの先にテレビ局全体の信頼回復がある。
- テレビ離れの拍車に危機感を持たなければならない事態。番組、報道関係なく厳しさを持って質を上げていく必要がある。社内の合意形成と風通しの良さが重要で、研修を通じた人材育成に取り組み、萎縮せず前向きな気持ちで企業活動を行って欲しい。良い意味での監視機能たる報道を通して、健全な発展や再生を後押ししていくような姿勢も必要。
- 公平な報道とか従来型の報道で、頭に縛られて時代の変化に追いつけていないことが起きている可能性がある。要因の一つとして、コンプライアンスへの過剰な意識もあるのでは。マスメディアが信頼できる情報源としての期待が確認できた一方、SNSが抱えている問題と同じものが地続きで存在していることに気づいた。
- 現状維持バイアスがあったからこそ起きた問題。若者が自由に意見を言える風通しの良い環境づくりや、自助努力、第三者によるコンプライアンス委員会の検討、定期的なチェックと情報公開が信頼回復につながる。真偽不透明な情報があるなかで、テレビは誠実な姿勢を保ち、過ちがあれば真摯に受け止めて改善し、クリーンなイメージを継続することが重要。